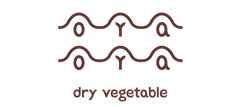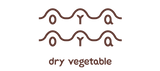干し野菜作り初心者必見!失敗しない7つのコツと基本の作り方
私は出張先の滞在ホテルで、離れて暮らす妹から嬉しいメッセージを受信した。
「お姉ちゃん!私ね、仕事の新企画でコンテンツ配信サービスの記事を任されることになったの!良かったら読んで感想を送ってくれない?」
妹は大学時代にアルバイトをしていた地域密着型の出版社に、ライターとして就職した。今年で入社して5年目を迎え、本人の頑張りがようやく実を結んだのだと私はなんだか妹が誇らしくてたまらなくなった。
私は自分が社会人5年目だった頃のことを思い出した。何かと覚えることの多い部署に配属された私は、自分の不器用さと融通の利かない性分によって、毎日とにかく四苦八苦していた。そんな私に比べ、妹はきっと柔軟性と素直さと持ち前の明るさで毎日仕事に奮闘しているに違いない。そう思った途端、妹が書いたという記事を読まずにはいられなくなった。ホテルのベッドに横になっていた私は飛び起きて、自分のノートパソコンを開いた。
「拝読するとしますか」
妹から送られてきたURLにアクセスすると、柔らかい色合いと温かみのあるイラストで彩られたページが表示された。
「へぇ……干し野菜ねぇ」
どうやら妹の担当する記事は「干し野菜」をテーマに、その作り方や食べ方、アレンジレシピなど、様々紹介しているらしい。《第1回 干し野菜の作り方》と銘打った記事をクリックした私は、自分の体がぐっと前のめりになり記事に釘付けになるのを自覚した。
「みなさん、これから【干し野菜】の魅力を少し、いいえ、たくさん私に語らせて下さい。」こんな挑戦的な書き出しから始まる妹の記事は、どこか拙さと初々しさと大胆さが入り混じったものだった。
妹の説明によると、干し野菜とはカットした野菜の水分を抜くことで栄養価を高め、うま味をぎゅっと閉じ込めた食材なのだそうだ。私たちの身近なところで言えば切り干し大根などが思い浮かぶ人も多いだろう。しかも驚いたのは、干し野菜は自宅で比較的簡単に、誰でも作ることが出来るということだ。
「へぇ!専門の施設でなきゃ作れないんだと思ってた……」
干し野菜は日光に当てて乾燥させるだけで作ることが出来、乾燥具合も日に当てる時間の長さによって調整出来るのだそうだ。ポイントは「野菜を干すためのざる」「風通し」「太陽光」、この3つを押さえれば自家製乾燥野菜が作れるというわけだ。
干す場所は陽の光がしっかりと当たる庭やバルコニーが適している。風通しが良いことも忘れてはいけない。
そして乾燥期間が数日にわたる場合、湿度が上がる夜間は室内保管をする必要があるのだそう。乾燥野菜作りに適した季節は、誰もが想像できるであろう「夏場」だ。連日の晴れ間が美味しい乾燥野菜を作るのに最適だ。注意するべきことは、天候の安定しない梅雨時期は避けておくのが吉であるということ。
記念すべき妹の第1回目の記事を読み終えた私の頭の中は、既に干し野菜をつくる計画でいっぱいだった。
「読んだわよ。早速、お天気アプリをダウンロードしちゃった。干し野菜にはお天気チェックが欠かせないんでしょ?」
私からの感想メッセージを読んだ妹からの返信が、あり得ないくらい早かったことは言うまでもない。
妹の連載記事を読むという楽しみと、乾燥野菜作りに挑戦するという課題を同時に手に入れた私。毎日がさらに忙しくなりそうだ。
第二話:室内で簡単!干し野菜の失敗しない作り方と4つの乾燥方法
干し野菜作りの基本!初めてでも失敗しない作り方
干し野菜作りは、思ったよりずっと簡単です。基本の作り方をマスターすれば、どんな野菜でも美味しく干せるようになりますよ。
まずは晴れた日を選びましょう。干し野菜作りには、日当たりと風通しの良い日が最適です。特に秋から冬にかけての乾燥した季節がおすすめ。午前10時から午後3時頃の日差しが強い時間帯に干すと、効率よく乾燥させることができます。
基本の干し野菜の作り方ステップ
-
野菜を洗って、皮をむかずにお好みの形にカットします
-
水分の多い野菜は、キッチンペーパーなどでしっかり水気を拭き取ります
-
ざるやネットに野菜が重ならないように並べます
-
日当たりと風通しの良い場所に置いて乾燥させるだけ!
干す時間は野菜によって異なりますが、セミドライなら半日〜1日、しっかり乾燥させるフルドライなら1〜2日が目安です。きのこ類など水分が少ない野菜は3時間程度、水分の多い野菜は6時間以上かけて干すといいでしょう。
 干し野菜作りに適した野菜は、基本的にはどんな野菜でもOK!でも初めての方には、きゅうり、大根、にんじんなどがおすすめです。生野菜との味の違いが大きく、干すことで驚くほど美味しく変身しますよ。
干し野菜作りに適した野菜は、基本的にはどんな野菜でもOK!でも初めての方には、きゅうり、大根、にんじんなどがおすすめです。生野菜との味の違いが大きく、干すことで驚くほど美味しく変身しますよ。
水菜やレタス、もやしなど、すぐに傷んでしまうデリケートな野菜は避けたほうが無難です。
失敗しない!干し野菜作りの7つのコツ
干し野菜作りは基本的には簡単ですが、ちょっとしたコツを押さえておくと、もっと美味しく仕上がります。初めての方でも失敗しないための7つのポイントをご紹介しますね。
1. 天気と時間帯を選ぶ
干し野菜作りには、晴れた日を選ぶのが鉄則です。特に日光がしっかりと当たる午前10時から午後3時頃の時間帯が最適。この時間帯は太陽の力が強く、効率よく水分を飛ばすことができます。
空気が乾燥している秋から冬にかけての季節がベストシーズン。湿度が高い梅雨時は避けたほうが無難です。
2. 切り方を工夫する
野菜の切り方は、干した後の使い道を考えて決めるといいですよ。短時間で乾燥させたいなら、薄めに切るのがポイント。
例えば、千切りなら漬物や炊き込みご飯に、薄い輪切りなら煮物やスープ、素揚げチップスに、厚めの輪切りならソテーや炒め物、揚げ物に向いています。
野菜は乾燥すると縮むので、少し大きめに切っておくのも忘れずに!
 3. 水分をしっかり拭き取る
3. 水分をしっかり拭き取る
特に水分の多い野菜(大根、トマト、きゅうりなど)は、干す前にキッチンペーパーなどでしっかり水気を拭き取っておきましょう。これだけで、綺麗に乾燥させることができます。
水分が残っていると、乾燥に時間がかかるだけでなく、カビの原因にもなりかねません。
4. 適切な間隔で並べる
野菜同士が重ならないよう、等間隔に並べるのが大切です。重なっていると、その部分だけ乾燥ムラができてしまいます。
通気性の良いざるや網の上に並べると、下からも空気が通って効率よく乾燥できますよ。
5. 夕方には取り込む
夕方から夜の間は湿度が上がりやすいので、干し野菜は室内に取り込みましょう。翌日また天気が良ければ、再び外に出して干します。
これを繰り返すことで、じっくりと均一に乾燥させることができます。
6. 乾燥具合をこまめにチェック
野菜の種類や大きさ、天候によって乾燥時間は変わってきます。こまめに触ってみて、乾燥具合を確認しましょう。
大根やピーマンはしんなりとしてフニャフニャに、にんじんやカボチャは全体が白っぽくカチカチになれば、ちょうど良い乾き具合です。
7. 保存方法にも気を配る
干し野菜は、しっかり乾燥させてから密閉容器や袋に入れて保存します。冷蔵庫なら5日ほど、冷凍庫ならセミドライで1週間、フルドライなら1ヶ月ほど保存できますよ。
湿気やホコリを避けるため、保存容器はしっかり密閉できるものを選びましょう。
あなたも、この7つのコツを押さえて、ぜひ干し野菜作りに挑戦してみませんか?
干し野菜の活用法!
料理がグッと美味しくなるレシピのヒント
せっかく作った干し野菜、どう料理に活かせばいいのか迷いますよね。干し野菜は旨味が凝縮されているので、様々な料理の味わいをグッと引き立ててくれるんです。
干し野菜の魅力は、何といっても調理時間の短縮!水分が少ないので味がしみ込みやすく、煮崩れもしにくいのが特徴です。炒め物なら火の通りも早くなり、油やガスの節約にもつながります。さらに、すでにカットしてあるので下ごしらえの手間も省けて、忙しい日の料理にぴったり!
干し野菜の基本の戻し方
干し野菜は、そのまま料理に使える場合もありますが、水で戻してから使うこともあります。戻し方は簡単!水またはぬるま湯に10〜30分ほど浸けておくだけです。野菜によっては硬さが残るので、その場合は様子を見て長めに水戻ししましょう。
戻し汁には旨味成分がたっぷり含まれているので、捨てずにスープや煮物の出汁として活用するのがおすすめですよ。
干し野菜を使った簡単レシピアイデア
-
干しキャベツ → スープや味噌汁の具材に
-
干し人参・干し大根 → 煮物や炊き込みご飯に
-
干しナス・干しかぼちゃ → 素揚げして和え物に
-
干し大根と油揚げの煮物 → 定番のお惣菜に
-
干しナスの味噌汁 → 香りが豊かに
-
干し人参と切り干し大根のサラダ → シャキッとした食感が楽しい
 冷蔵庫に残ったキャベツの外葉、人参や大根の切れ端、形の不揃いなナスやズッキーニ…。通常なら捨ててしまうような野菜も、干し野菜にすれば立派な食材に生まれ変わります。
冷蔵庫に残ったキャベツの外葉、人参や大根の切れ端、形の不揃いなナスやズッキーニ…。通常なら捨ててしまうような野菜も、干し野菜にすれば立派な食材に生まれ変わります。
「もったいない」を「おいしい」に変える干し野菜作り。あなたの食卓にも、ぜひ取り入れてみてくださいね。
干し野菜作りでよくある失敗とその対処法
干し野菜作りに挑戦してみたものの、うまくいかなかった…という経験はありませんか?初めてのことだと、ちょっとした失敗はつきものです。でも大丈夫、対処法を知っておけば次回は成功間違いなし!
よくある失敗と、その対処法をご紹介します。
カビが生えてしまった!
干し野菜にカビが生えてしまう主な原因は、乾燥が不十分だったり、保存環境に湿気があったりすることです。対処法としては、干す前にしっかり水気を拭き取ること、天気の良い日を選ぶこと、そして十分に乾燥させてから保存することが大切です。保存容器も清潔で乾いたものを使いましょう。
もし少しでもカビを見つけたら、残念ですがその干し野菜は処分するのが安全です。
乾燥ムラができてしまった
野菜の厚みにばらつきがあったり、干す際に重なっていたりすると、乾燥ムラができてしまいます。
均一な厚さに切ること、そして干すときは野菜同士が重ならないよう等間隔に並べることを心がけましょう。また、乾燥の途中で裏返してあげると、より均一に乾燥させることができますよ。
硬くなりすぎた・パサパサになった
干しすぎると野菜が硬くなりすぎたり、パサパサになったりすることがあります。
セミドライ(半乾き)の状態で使いたい場合は、乾燥時間を短めにして、こまめに状態をチェックしましょう。また、戻すときはぬるま湯を使うと早く戻りますよ。
硬くなりすぎた干し野菜も、長めに水に浸けることで十分美味しく食べられます。むしろ、しっかり乾燥したものは長期保存に向いているんです。
虫がついてしまった
外で干していると、虫が寄ってくることもあります。
天日干し用のネットを使うか、清潔なガーゼなどをかけて干すと安心です。また、干す場所の周りを清潔に保つことも大切ですよ。
干し野菜作りは、少しの工夫と経験を重ねることで、どんどん上達していきます。失敗してもめげずに、ぜひ続けてみてくださいね!
まとめ:干し野菜で食卓に小さな豊かさをプラス
干し野菜作りは、特別な道具や技術がなくても、誰でも簡単に始められる素敵な食の習慣です。野菜を切って干すだけという単純な工程ながら、その効果は絶大。旨味と栄養が凝縮され、長期保存も可能になり、何より新鮮な野菜とはまた違った美味しさが楽しめます。
今回ご紹介した7つのコツを押さえれば、初心者の方でも失敗なく美味しい干し野菜が作れるはず。天気と時間帯を選び、切り方を工夫し、水分をしっかり拭き取り、適切な間隔で並べ、夕方には取り込み、乾燥具合をこまめにチェックし、保存方法にも気を配る。この基本を守れば、きっと素晴らしい干し野菜ライフが始まりますよ。
ーパーでは手に入らない乾燥野菜を食べてみたくなったら、もちろん自作してみるのもおススメです。作り方はとっても簡単!洗った野菜の水気を拭いて、切った野菜を風通しと陽当たりのいい場所で天日干しするだけ。
自作できるようになるまで待てない!というアナタは、ぜひ[OYAOYA]の乾燥野菜を召し上がれ。