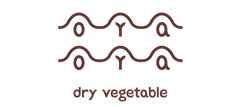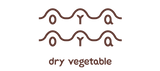室内で簡単!干し野菜の失敗しない作り方と4つの乾燥方法
「ありがとうございます。ご苦労様です」
私は配達業者さんから少し大きめの茶色の段ボール箱を受け取ると、両腕に抱えて足早に玄関からリビングへと移動した。
「フフン、来た来た!」
私は箱の中に綺麗に収められた、直径40cm弱の「干し野菜カゴ」を取り出した。
「これがなくちゃ始まんないのよね」
私は今まさに新しい趣味に挑戦しようとしているのだ。というのも、出版社でライターとして働いている妹が、「干し野菜」に関する記事を連載することになり、それを読んだ私はたちまち自宅で「干し野菜」作りをしようと思い立ったのだった。
干し野菜は道具と環境が整えば誰でも簡単に自宅で作ることが出来る。揃えておく必要がある道具に野菜を干すための「ザル」があり、私はすぐさま良さそうな商品をネットで探し当てた。
干し野菜作りには、通気性の良いザルや網を用いる。室内で作る場合、それらのザルもしくは網の上に、ちょうど良い大きさにカットした野菜を並べ、扇風機やサーキュレーターを使って風を当てる。こうすることで、満遍なく野菜を乾燥させることが出来る。こうした段取りを踏むことで室内でも比較的簡単に乾燥野菜を作ることが出来るのだそうだ。
もし日当たりの良い場所が確保出来るなら、窓辺にザル、網を設置し自然光に当てるという方法もある。屋内で乾燥野菜を作る場合は、こうした2種類の方法によって作ることが出来るのも、非常にありがたい。
《注意するべき点は、カットした野菜を並べる際に野菜どうしが重ならないようにすること!湿気は大敵です!》
妹の記事を読みながら「ほぉ」と思わず声が出てしまう。
「子どもの頃は私があの子に勉強教えてあげてたんだけどなぁ」
私は子ども時代の妹と自分のことを思い出しながら、嬉しいような少し寂しいような、それでいて妹のことが誇らしいような、複雑で温かい気持ちに包まれた。
「室内での干し野菜の作り方の記事、とっても分かりやすくて読みやすかったわよ」
妹に宛てたメッセージに、届いた干し野菜カゴの写真を添えて送信した。その夜、ものぐさな姉が干し野菜作りに目覚めたことに妹が度肝を抜かれたことは想像に難くない。
「どんな野菜で干し野菜を作ろうかしら?」
私の新しい趣味はまだ始動したばかりだ。
第三話:マンションのベランダで干し野菜作り!都会派の新習慣ガイド
 失敗しない干し野菜の基本の作り方
失敗しない干し野菜の基本の作り方
干し野菜作りは本当に簡単です。野菜を切って、風通しのいい場所に並べるだけ。特別な道具も必要ありません。
まずは、使う野菜を選びましょう。スーパーで買った野菜はもちろん、冷蔵庫に残った野菜や、皮や茎などの捨てがちな部分も立派な材料になります。おすすめの野菜はこちら
野菜は洗って水気をしっかり拭き取ります。水分が残っていると乾燥に時間がかかるだけでなく、カビの原因にもなりますので要注意。根菜類は皮のまま使うこともできますが、土がついていたらしっかり洗い落としましょう。
 次に、野菜を均一な厚さに切ります。厚さは5mm〜1cm程度が目安。薄すぎると乾燥しすぎて風味が飛んでしまい、厚すぎると乾きムラができやすくなります。切った野菜は、ざるやネット、干しかごなど通気性のよいものに重ならないように並べます。野菜同士が重なると乾きムラの原因になるので、少し間隔をあけて並べるのがコツです。
次に、野菜を均一な厚さに切ります。厚さは5mm〜1cm程度が目安。薄すぎると乾燥しすぎて風味が飛んでしまい、厚すぎると乾きムラができやすくなります。切った野菜は、ざるやネット、干しかごなど通気性のよいものに重ならないように並べます。野菜同士が重なると乾きムラの原因になるので、少し間隔をあけて並べるのがコツです。
あとは風通しのよい場所に置いて、乾くのを待つだけ。どのくらい乾かすかは、使い方によって調整しましょう。セミドライなら数時間〜半日、しっかり乾燥させるなら1〜2日ほどかかります。天候や気温、湿度によっても変わってきますので、時々様子を見てくださいね。
どう思いますか? 意外と簡単でしょう?
4つの乾燥方法とそれぞれの特徴
干し野菜を作る方法は、実はいくつかあります。それぞれの特徴を知って、自分の環境や目的に合った方法を選んでみましょう。
1. 天日干し(屋外乾燥)
最も伝統的な方法が天日干し。太陽の光と風を利用して野菜を乾燥させます。
カラッと晴れた日に、ベランダや庭など日当たりと風通しのよい場所で行うのがベスト。太陽の紫外線には殺菌効果もあるので、衛生的に乾燥させることができます。ただし、虫や鳥、ホコリから守るために干しかごやネットを使うといいでしょう。
天日干しの最大の魅力は、太陽の恵みを受けながらゆっくりと水分を失うことで、野菜の風味が増すこと。特に根菜類やきのこ類は天日干しで甘みが増します。でも、雨や湿度に左右されるのがネックですね。
2. 室内干し(陰干し)
天候に左右されず、いつでも干し野菜が作れるのが室内干しのメリット。窓際など明るく風通しのよい場所を選びましょう。
エアコンの風が直接当たる場所は避け、扇風機などで緩やかに空気を循環させるとより効果的です。室内干しは天日干しよりも乾燥に時間がかかりますが、野菜の色が鮮やかに保たれる利点があります。
冬場の乾燥した季節は特に室内干しに向いています。湿度の高い梅雨時期は除湿機を併用するとよいでしょう。
 3. 電子レンジ乾燥
3. 電子レンジ乾燥
時間がないときに便利なのが電子レンジを使った乾燥方法。短時間でセミドライ状態の干し野菜が作れます。
野菜を薄く均一に切り、キッチンペーパーを敷いた耐熱皿に重ならないように並べます。500W〜600Wで2〜3分加熱し、一度取り出して様子を見ます。まだ湿っていれば、さらに30秒〜1分ずつ加熱を繰り返しましょう。
電子レンジ乾燥は短時間で済む反面、乾きムラができやすいのが難点。また、完全に乾燥させるのは難しいので、セミドライ状態で冷蔵保存し、早めに使い切るのがおすすめです。
4. 食品乾燥機を使用
最も手軽で確実なのが食品乾燥機を使う方法。温度と時間を設定するだけで、均一に乾燥した干し野菜が作れます。
一般的な家庭用食品乾燥機は35℃〜70℃の温度設定が可能で、野菜の種類に合わせて調整できます。低温でじっくり乾燥させると、野菜本来の風味や色が保たれます。
初期投資は必要ですが、天候に左右されず、衛生的に干し野菜が作れるのが魅力。特に干し野菜作りを本格的に始めたい方にはおすすめです。
私自身は、晴れた日は天日干し、雨の日や忙しいときは室内干しと電子レンジを併用しています。その日の天気や予定に合わせて、臨機応変に方法を選ぶのがコツですよ。
干し野菜作りのよくある失敗と対策
初めて干し野菜を作るとき、いくつか注意したいポイントがあります。よくある失敗とその対策をご紹介しますね。
まず、乾燥不足による腐敗。しっかり乾いたように見えても、中に水分が残っていると、カビや腐敗の原因になります。野菜の中心部まで乾いているか確認し、少し硬めになるまで乾燥させましょう。
逆に、乾燥しすぎて風味が飛んでしまうことも。特に香味野菜(ハーブ類など)は乾燥しすぎると香りが失われます。用途に合わせて乾燥具合を調整するのがコツです。
乾燥ムラも失敗の一つ。野菜の切り方が不均一だったり、重なって干したりすると、部分的に乾き具合が異なってしまいます。均一な厚さに切り、重ならないように並べることが大切です。湿気の多い日に干すと、乾きにくいだけでなく、雑菌が繁殖するリスクも高まります。晴れた日や湿度の低い日を選び、室内なら除湿機や扇風機を活用しましょう。
これらのポイントに気をつければ、失敗なく美味しい干し野菜が作れますよ!
まとめ:干し野菜で食生活をもっと豊かに
干し野菜作りは、特別な道具も専門知識も必要ない、誰でも始められる食の知恵です。野菜を切って干すという単純な作業が、食材の価値を高め、食生活を豊かにしてくれます。
規格外野菜や余りがちな野菜を干すことで、食品ロスを減らし、栄養価の高い食材を長期保存できる。そして何より、干すことで野菜本来の甘みや旨味が凝縮され、新しい美味しさに出会えるのが魅力です。
天日干し、室内干し、電子レンジ、食品乾燥機と、環境や目的に合わせた方法を選べるのも嬉しいポイント。初めは簡単な野菜から始めて、少しずつレパートリーを増やしていくのがおすすめです。
日々の食卓に、ちょっとした工夫と豊かさをプラスする干し野菜の世界。あなたも今日から、干し野菜ライフを始めてみませんか?