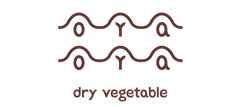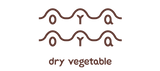干し野菜に最適な野菜10種類!初心者でも失敗しない選び方
週末、私は会社の同僚3人と定例で開いているランチ会に参加していた。ランチ会といえどそんな肩の張る会ではない。参加メンバーのひとりが好きな店を予約し、そこで軽く仕事の報告と称した、日常の悩みや愚痴、思いのたけを存分に語り合うのだ。
「私たち同期もそろそろ中堅よね」
「私の部署の吉田さん、来月結婚ですって」
「姪っ子が来年、小学校なの」
そんななんてことないトークテーマで、私たちは3時間話し倒しているのである。そしてこの日、ひとりの同期がこんな話を始めた。
「私最近、飼ってるワンコに手作りご飯あげてるんだ」
彼女の話によると、飼っている犬がシニア期を迎え、体調管理の一貫として食生活の見直しを図っているのだそうだ。
「それがなかなか面白くって、毎日献立考えるのが楽しみなの」
「ふふ、献立考えるのがワンコの、だなんてねぇ、ははは」
「なによ、私たち全員独身じゃないの!あんただって人のこと笑ってられないわよ」
友人たちがじゃれ合うのを眺めながら、私はふと自分が作っている干し野菜のことを思い出した。
「あ、そう言えば私、最近干し野菜始めたんだよね」
私の言葉に友人は目を丸くして体を乗り出した。
「干し野菜?あんた、新しいビジネスでも始めたの?」
「違うわよ。休日のお天気がいい日に、家で干し野菜作ってるの」
私は妹の連載記事のこと、私が作っている干し野菜のことを同期たちに大まかに話して聞かせた。
「それ、どんな野菜で作ってるの?」
友人の質問に、妹のこんな記事を思い出した。
《干し野菜、始める前にチェックしておくこと!干し野菜にも向き不向きな野菜があります。ビギナーさんに先ず試してもらいたい野菜、それはズバリ根菜類です。大根、ニンジン、ごぼう、れんこん。これらの野菜は干し野菜に特に向いているんです。なぜなら、それは水分量!これらの根菜類は水分量が少なく、乾燥させた時に旨味がぎゅっと凝縮され、初心者の人にも簡単に美味しく作ることが出来るからです!ほかにもきのこ類も水分量控えめでおすすめです。乾燥させることできのこの風味が豊かになり、香りがたって美味しいですよ!》
私からのおすすめもひとつ。
「ナスとピーマンも乾燥させると食感と風味に変化が出ておすすめよ」
ランチ会も終盤にさしかかり、私たちはカフェに移動してゆっくり話しをすることにしたのだった。
干し野菜の魅力と基本の知識
干し野菜作りに必要なのは、野菜と干す場所だけ!特別な道具は必要なく、ざるやネットがあれば誰でも簡単に始められます。朝から夕方まで天日干しすれば、半生タイプの干し野菜が完成。乾物のようにカラカラに干すなら、もう少し時間がかかりますが、半生タイプなら半日もあればOKなものもあるんですよ。
干し野菜のメリットは、なんといっても野菜の旨味アップと長期保存ができること!野菜本来の旨味を太陽と風の力を借りて中にぎゅーっと閉じ込めるので、あれやこれやと調味料を足さなくても出汁が出て、薄味でもとってもおいしいんです。また、料理のレパートリーが少なくて毎日の献立に頭を悩ませている方にもおすすめ。同じ調理法でも干し野菜を使えば食感や風味が異なり、新鮮な一品が完成しますよ。
干し野菜に最適な野菜10種類
干し野菜初心者さんが「何から始めればいいの?」と思ったら、まずは水分の少ない野菜からチャレンジするのがポイントです!水分が多い野菜は乾燥に時間がかかり、湿度が高い日が続くとカビの原因になることも。
そこで、初心者さんでも失敗しにくい干し野菜におすすめの野菜10種類をご紹介します。これらの野菜は乾燥しやすく、干した後の味わいも格別なんですよ!
1. 大根
干し大根は切り干し大根として馴染み深い野菜です。皮付きのまま3〜4mm幅の輪切りや千切りにして干すと、甘みが増して美味しさアップ!煮物や炊き込みご飯に使うと、出汁がよく出て味わい深い一品になります。大根の皮目は栄養満点なので、あえて皮付きのまま干すのがおすすめ。これぞ、干し野菜の醍醐味です!
干し大根を油揚げと一緒に煮れば定番のお惣菜に。水で戻してから使うと煮崩れしにくく、味もしみやすいので、時間があるときは少し水で戻してから調理するといいですよ。
2. にんじん
にんじんも皮付きのまま干すのがおすすめ。乱切り、格子切り、千切りなど、使いたい料理に合わせて切り方を変えると便利です。半日ほど干すとかなりクシャッと水分が抜け、かさが減るのがわかります。
干したにんじんはところどころに黒ずみが現れることがありますが、これはカビではなく自然な現象なので気にせず食べて大丈夫!干し人参は切り干し大根と合わせてサラダ風にすれば、シャキッとした食感が楽しめます。煮物や炊き込みご飯にも最適で、甘みが増して子どもにも人気の食材になりますよ。
3. かぼちゃ
かぼちゃは水分が少なく、甘みが強い野菜なので、干し野菜初心者さんにぴったり!皮ごと薄切りにして干すと、甘みが凝縮されてまるでお菓子のような美味しさになります。
干しかぼちゃは素揚げしてそのまま食べても絶品。サクサクとした食感と自然な甘みが口いっぱいに広がります。また、煮物に入れると煮崩れしにくく、ホクホクとした食感を楽しめますよ。我が家では、干しかぼちゃをみそ汁に入れるのが定番。出汁要らずで深い味わいのみそ汁ができあがります。
4. きのこ類(しいたけ、しめじなど)
きのこ類は元々水分が少ないので、干し野菜にするのにぴったり!石づきを取ってほぐしたり、スライスしたりして干すだけで、旨味がぐっと増します。しいたけは丸ごと干しても、スライスして干してもOK。干ししいたけの香りは格別で、どんな料理も一気に本格的な味わいにしてくれます。
干したきのこ類は冷凍保存もできるので、買ったのに使い切れずにダメにしてしまった…という経験がある方は、干してから冷凍しておくといいですよ。スープや味噌汁、炊き込みご飯など、あらゆる料理の味わいをワンランクアップしてくれる万能選手です!
5. さつまいも
つまいもも水分が少なく、干し野菜にすると甘みが増す野菜です。薄く輪切りにして干すと、水分が抜けてかさが減り、料理に使いやすくなります。炒め物や煮物に加えると、煮崩れしにくく、ほっくりとした食感と自然な甘みが楽しめます。
おやつとして楽しむ場合は、そのまま干すのではなく、蒸したり加熱してから干す「干し芋」にするのがおすすめ。砂糖不使用でもしっとりとした甘さが引き出され、子どもにも人気のおやつになりますよ。
 6. れんこん
6. れんこん
れんこんは薄切りにして干すと、シャキシャキとした独特の食感がさらに楽しめるようになります。れんこんの穴が特徴的な見た目も、干すことでより際立ちますよ。
干したれんこんは素揚げしてチップスにすると絶品!サクサクとした食感と自然な甘みが口の中に広がります。また、煮物や炒め物に加えると、シャキシャキとした食感が残り、料理に変化をつけられます。れんこんに含まれるタンニンは渋みの元になるので、切ったらすぐに酢水にさらしてから干すと、変色を防ぎ、きれいな仕上がりになりますよ。
7. なす
なすは水分が多い野菜ですが、薄く輪切りにして干すことで、驚くほど味わい深い干し野菜になります。干すことでなすの水分が抜け、旨味が凝縮されるんです。
干したなすは味噌汁に入れると香りが豊かになります。また、油で揚げて和え物にすると、なすの風味が存分に楽しめる一品に。なすは変色しやすいので、切ったら酢水に15分ほど浸けてから水気を拭き取り、干すと色よく仕上がります。黒っぽくなっても味には問題ないので、気にならない場合は酢水に浸けなくてもOKですよ。
8. ズッキーニ
ズッキーニは夏野菜の代表格ですが、実は干し野菜にもぴったり!薄く輪切りにして干すと、水分が抜けてかさが減り、旨味が凝縮されます。
干したズッキーニは素揚げしてチップスにすると、サクサクとした食感と自然な甘みが楽しめます。また、パスタやスープに加えると、ズッキーニの風味がしっかりと感じられる一品に。夏に大量に収穫されるズッキーニを干し野菜にすれば、長期保存ができて無駄なく使い切れますよ。
9. トマト
トマトは水分が多いため、干し野菜にするときはスライスして薄めに切るのがポイント。湿度が高い日や風通しの悪い場所ではカビが発生しやすいので、必ず日当たりと風通しの良い環境で干しましょう。
干すことで水分が抜け、甘みと酸味がぎゅっと凝縮されます。セミドライトマトにすれば、パスタやサラダ、パンの具材として大活躍。オリーブオイルに漬け込めば、保存性が高まり風味も一層豊かになります。
10. キャベツ
キャベツの外葉など、普段なら捨ててしまいがちな部分も干し野菜にすれば大変身!一口大にちぎるか、食べやすい大きさに切って干すだけで、旨味が凝縮された干しキャベツの完成です。
干したキャベツはスープや味噌汁の具材として最適。水分が抜けているので、煮崩れしにくく、キャベツの甘みをしっかりと感じられます。また、炒め物に加えると、かさが減っているので大量に使えて、栄養たっぷりの一品になりますよ。
干し野菜作りのコツと保存方法
干し野菜作りに適した時期は、晴れが多い春、強い日差しが降り注ぐ夏、空気が乾燥する冬です。曇りや雨が続き湿度の高い時期は、カビが生えやすいため避けましょう。天日干しは10〜15時が最適!よく晴れた日の日光がよく当たる朝10時から15時頃が干し野菜作りのベストタイムです。
干し野菜作りの基本手順はとってもシンプル。「野菜を洗う→水気をふく→切る→風通しがよく日の当たる場所に干す」の工程のみ。野菜を干す前に、キッチンペーパーなどでしっかり水気を拭かないとカビの原因になりかねませんので、ここは丁寧に処理しましょう。
干し野菜の保存方法は、乾燥具合によって変わります。セミドライタイプ(半生)は清潔な容器や袋に入れて冷蔵庫で保存し、4〜5日で食べきりましょう。生の野菜と同じように使えるので、料理の幅が広がりますよ。
ドライタイプ(しっかり乾燥)は清潔な密閉容器や瓶に入れて、常温または冷蔵庫で保存しましょう。状態がよければ最長3ヶ月ほど保存可能です。冷蔵庫に入れる場合は、結露に注意してください。5〜15分ほど水で戻し、やわらかくしてから調理することもできます。
しかし干す環境や、乾き具合で変わるのであくまで目安にして、適宜野菜の状態を見て食べられるかの判断するようにしましょう!
まとめ:干し野菜で食卓に小さな豊かさを
干し野菜は、野菜本来の旨味を凝縮させ、長期保存を可能にする素晴らしい食材です。特に初心者さんには、きのこ・かぼちゃ・大根・にんじん・さつまいもなど、水分の少ない野菜からチャレンジしてみてください。失敗が少なく、成功体験を積み重ねられますよ!
干し野菜作りは広い庭が必要だったり、野菜を何度もひっくり返したりともっと大がかりなものだと思っていました。けれど実際にやったことは、野菜を切って竹ざるで干すだけ。あとはベランダのちょっとしたスペースに放置しておくだけで、かなりお手軽!
スーパーでは手に入らない乾燥野菜を食べてみたくなったら、もちろん自作してみるのもおススメです。作り方はとっても簡単!洗った野菜の水気を拭いて、切った野菜を風通しと陽当たりのいい場所で天日干しするだけ。自作できるようになるまで待てない!というアナタは、ぜひ[OYAOYA]の乾燥野菜を召し上がれ。